はじめに:妊活において“ただ寝て待つ”はもったいない
妊活(妊娠を意図的に準備する段階)に取り組もうと思ったとき、「栄養」「排卵」「ストレス管理」などさまざまな要因が気になります。運動もその1つ。「運動していいの? 逆に影響するんじゃないか?」という不安を抱える方も多いでしょう。
でも、適度な運動は実は妊娠力(妊娠しやすさ)をサポートする可能性があり、日常にうまく取り入れることで“体を妊娠モードに整える”手助けになります。本記事では、最新の知見を交えながら、妊活における運動のメリット・方法・注意点を整理してお伝えします。
妊活と運動:なぜ関係があるのか

まずは、なぜ「運動」が妊活に関係するのか、そのメカニズムや理論背景から見ていきましょう。
血流改善・子宮・卵巣環境の向上
有酸素運動などで全身の血流がよくなると、子宮や卵巣への酸素・栄養供給が改善されやすくなるという考えがあります。実際、妊活中に適度な運動を取り入えることで、血流促進を通じて卵巣や子宮機能改善が期待できるという報告もあります。
また、股関節や下半身の筋肉を使う運動(スクワット、ランジなど)を取り入れると、骨盤周辺の血行促進を意識でき、子宮・卵巣への血流に寄与する可能性も指摘されています。
ホルモンバランス・排卵機能への効果

運動はインスリン感受性を改善したり、体脂肪をコントロールする作用が知られており、これがホルモンバランスを整える助けになることがあります。肥満や代謝異常は性ホルモンのアンバランスを引き起こし、排卵障害のリスクを高めるため、適切な体重管理は妊活の重要な要素です。
一方で、ある研究では、週あたり1時間の強度運動を追加するごとに、無排卵性不妊リスクが 7 % 減少、という結果もあったことが報告されています。
ストレス軽減・自律神経調整

妊活は心理的負荷が高くなることが多く、ストレスがホルモン系に悪影響を及ぼす可能性があります。運動はストレスホルモン(たとえばコルチゾール)を抑え、エンドルフィンやリラックス系の神経伝達物質を増やすことで、自律神経やホルモン環境を整える補助になると期待されます。
このように、運動には妊活の“バックグラウンド的な支え”としてさまざまな作用が見込まれます。ただし、すべての運動が良いわけではなく、「適度さ」が極めて大事になってきます。
運動の“適度さ”が肝心:過度な運動はかえってリスクに

運動を“多ければ多いほどいい”と単純に思うのは危険です。妊活中〜排卵・着床期には、激しい運動が逆効果になりうるという報告もあります。
過度な運動が妊活に与えるリスク
- ある前向きコホート研究では、強度の高い運動(1年に4時間以上の高強度運動を続けた群)は、卵胞発育の停止や着床失敗率の増加、ライブ出産率の減少と関連があった、という報告があります。
- 激しい運動が卵巣や子宮への血流をそらしてしまったり、体のエネルギー消費が多くなりすぎて排卵システムが抑制される可能性が論じられています。
- 妊娠が成立しやすい時期(排卵期〜黄体期など)には、強度の高い運動は子宮内膜や着床を妨げる可能性を懸念する声もあります。
適度の目安:どのくらいが“ちょうどいい”か
適度とされる運動量・強度の目安は、以下のようなガイドラインが参考になります:
| 指標 | 内容・例 |
|---|---|
| 運動時間目安 | 週あたり合計 150 分程度の中強度運動(例:1日30分 × 5日) |
| 強度目安 | 中強度:息がやや速くなるが “会話できるレベル” まで(軽く息が弾む程度) |
| 運動の種類 | 歩く、ゆるやかなジョギング、サイクリング(軽め)、水泳、ヨガ、ピラティスなど“身体への衝撃が少ない”運動が中心に推奨 |
| 運動頻度 | “毎日” ではなく、回復日を設けたり、無理のない範囲で継続できる頻度が望ましい |
つまり、たとえば「1日30分程度、息が少し弾むくらいのウォーキングや軽いジョギング、ヨガ」といったアプローチが、妊活フェーズには実用的で体にも優しい線と言えます。
妊活期におすすめの運動メニュー・実践例
具体的にはどんな運動を、どのように取り入れたらいいか、妊活段階別・目的別に整理してみます。
運動スタート時の導入メニュー(初心者向け)
妊活を始めたばかり、もしくは長らく運動していなかった人向けに、無理なく始められる内容を:
- ウォーキング(速歩):まず週3〜4日、20〜30分を目標に。公園や散歩道を活用。
- ヨガ / ストレッチ:呼吸法やゆるやかな動きを取り入れ、自律神経を整える目的で。
- 軽い筋トレ(自重):スクワット、ランジ、ヒップリフトなど、股関節・下半身を中心に。子宮・卵巣付近の血流を意識。
- ピラティス:体幹を整え、骨盤底筋への刺激も期待できる。
これらを無理のない頻度で組み合わせ、途中で体調の変化に応じて調整します。
妊活中〜排卵期・着床期の運動例
妊娠成立に向けた期間(排卵期、着床期)では、以下を意識して調整を:
- 強度を少し抑える(例:ジョギング → 速歩、VI(強度インターバル運動)は控える)
- 衝撃系運動(ジャンプ、激しいダンス、ハードなHIITなど)は避ける
- 運動時間も30分以内、場合によっては20分前後に抑えるようにすることも多いです。
- 強いねじり動作、激しい腹圧がかかる運動は控える
- 有酸素運動+軽い筋トレのミックスが無理が少ない組み合わせ
不妊治療中・体調変化期の運動調整
体外受精(IVF)や人工授精(IUI)などを行っている場合は、治療スケジュール・体調変化に応じて以下のような配慮をすべきです:
- 刺激排卵期・採卵直前〜採卵後は卵巣腫大・捻転リスクを考え、強度の高い運動は控えるべき。
- 運動時間を30分程度にとどめ、ゆるやかなものに限定する指導例が多いです。
- 移植後(胚移植直後など)は、温熱(サウナ・激しい運動による体温上昇)も配慮すべきとの声もあります。
- 医師の指導や個別の体調管理を最優先すること
実践例:1週間プラン(モデルケース)
下記はあくまで「無理のない範囲での例」で、体調や治療段階によって調整が必要です:
| 曜日 | 運動内容 | 時間・強度 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 月曜 | 速歩ウォーキング | 30分 | 最初の15分はウォームアップ、後半少し速めに |
| 火曜 | ヨガ / ストレッチ | 20〜30分 | 呼吸を意識したゆる運動 |
| 水曜 | 軽めの筋トレ(スクワット、ランジ) | 各10回 × 2〜3セット | 無理せず、呼吸/フォーム重視 |
| 木曜 | 速歩ウォーキング | 30分 | できれば自然の中で歩けるコースを選ぶ |
| 金曜 | ピラティス | 20〜30分 | コア・骨盤底筋を意識 |
| 土曜 | 軽いサイクリング / 水泳 | 30分 | 衝撃少なめの運動でリラックス感も重視 |
| 日曜 | 休息日または散歩 | — | 体を休める日を必ず確保 |
このように「無理がない頻度・強度」でバランスをとることが妊活運動継続の鍵です。
運動を取り入れる上での注意点・リスク管理

運動には“適度”が最重要ですが、それ以外にも気をつけたい点があります。
自己判断せず医師と相談を
- 特に不妊治療中や過去の婦人科トラブル(子宮筋腫、卵巣嚢腫、子宮腺筋症、子宮奇形など)がある方は、運動内容について担当医・生殖医療医と相談を必ず行うべきです。
- 治療サイクルとの兼ね合いで、運動を控えるべき時期があるため、専門家の判断が優先されます。
体調変化・違和感に敏感になる
運動中または後に次のような症状が出たら、すぐ中断・医療機関受診を考えましょう:
- 腹痛、下腹部痛、強い張り感
- 出血(特に治療後期)
- めまい、気分不良、動悸
- 強い疲労感、回復しにくい筋肉痛
栄養補給・水分補給を十分に
運動をすることでエネルギー消費が増えるため、栄養バランスを保つことは非常に重要です。特に妊活期は“低カロリーで運動量を稼ぐ”という極端なダイエットは禁物です。
また、脱水傾向になると血流や代謝に悪影響を及ぼす可能性もあります。
妊活×たんぱく質に関する記事→https://www.maternity-university.com/wp-admin/post.php?post=822&action=edit
睡眠・休息も運動効果を支える
運動だけでなく、質の良い睡眠・休息も妊活には不可欠です。体は回復を通じてホルモン系・細胞修復が行われるため、運動と休息のバランスがとれてこそ良い結果につながります。
よくある質問

Q. もともとランニングをしていたが、妊活中も続けていいか?
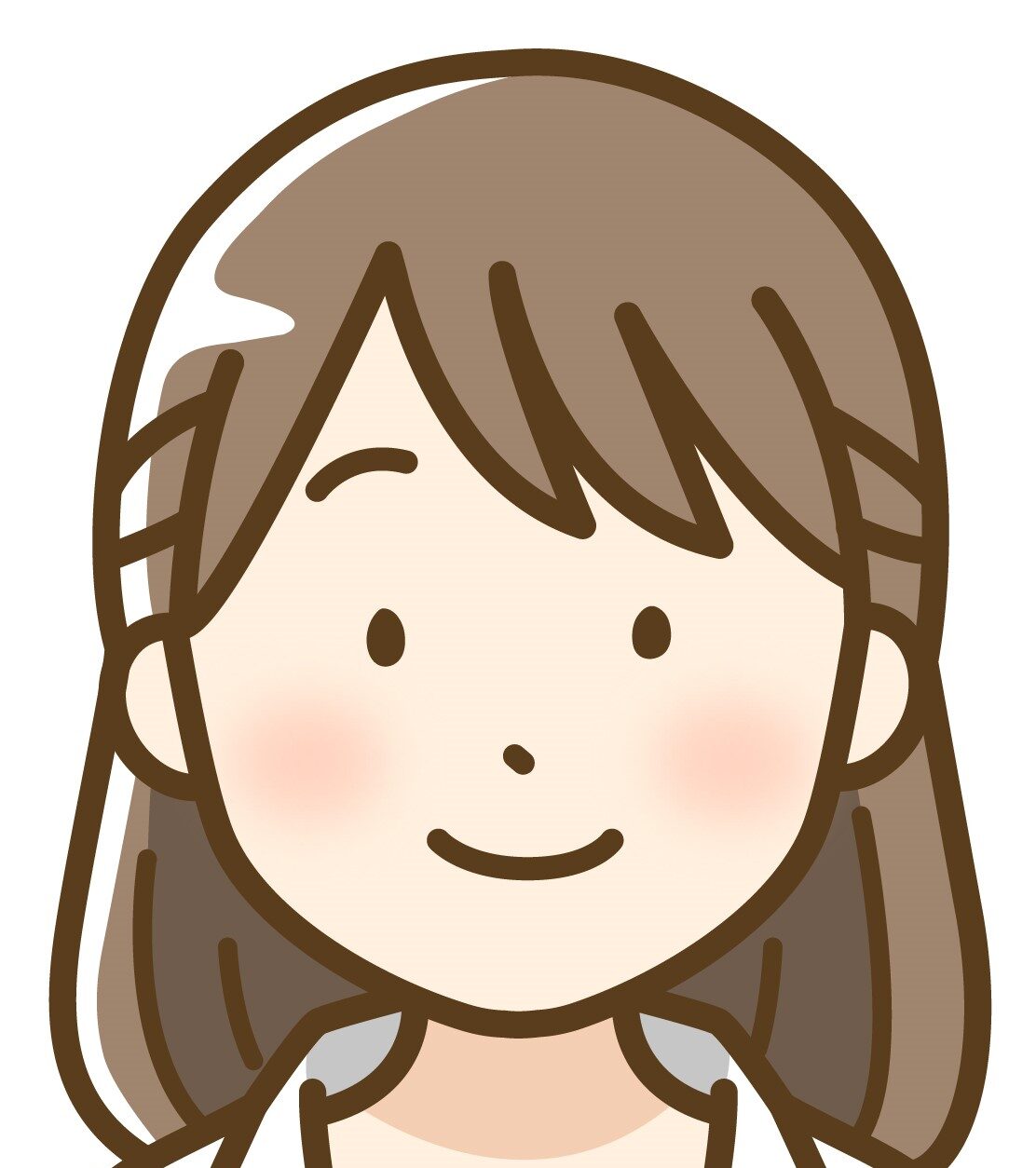
答えとしては「強度を下げて継続する」は可能ですが、無理のない範囲での調整が必要です。急に強度を上げすぎると、体がストレスと認識してしまう恐れがあります。
また、妊娠可能期(排卵期〜着床期)は少しセーブしたほうがいい、という専門家意見もあります。

Q. 運動だけで体重改善できるか? 食事はどうするべき?
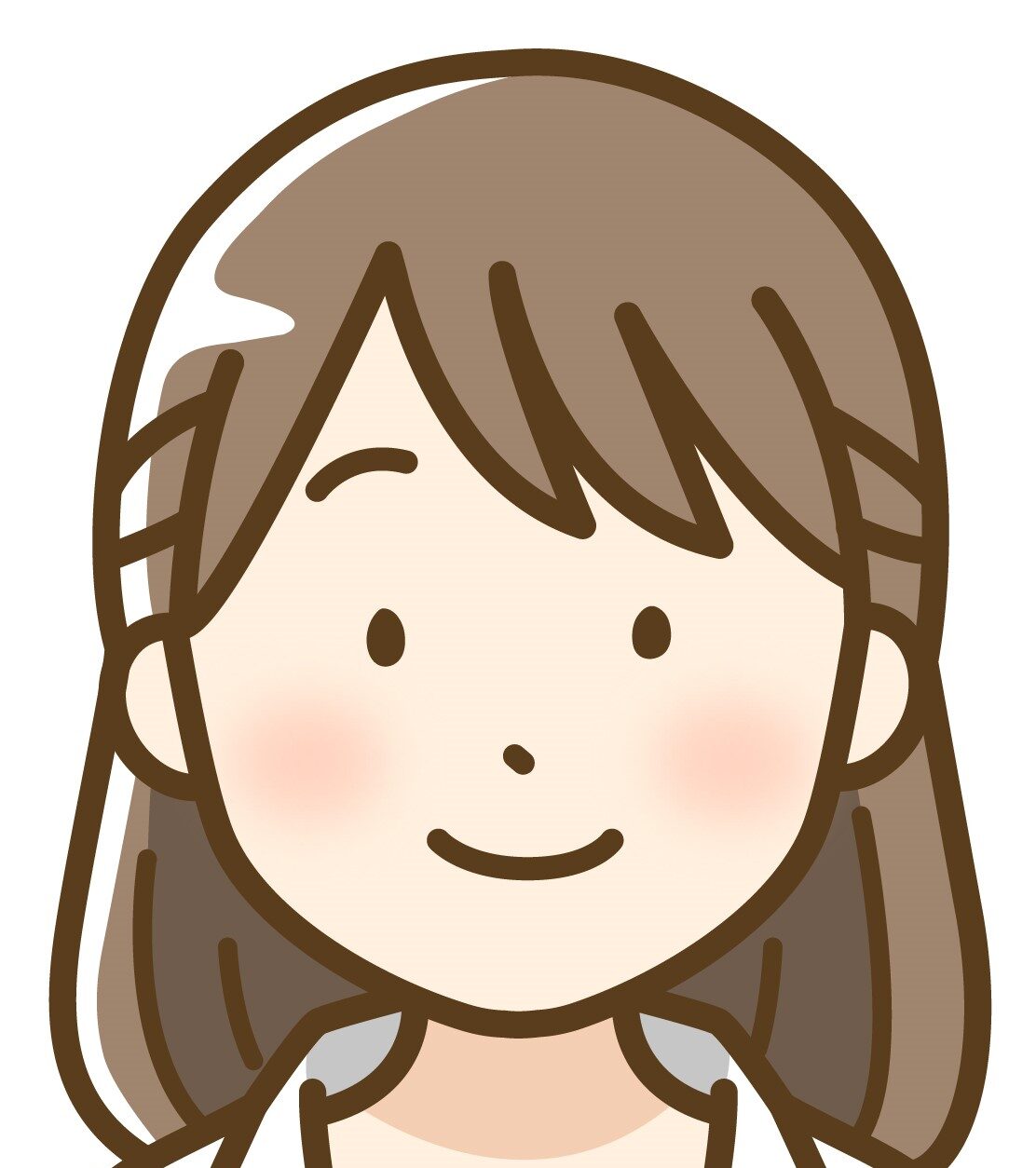
運動は体重管理の一要素にすぎません。妊活期には「適正体重」を維持することが重要で、食事・睡眠・ストレス管理と総合的に取り組むべきです。例えば、栄養素の偏りがないようにタンパク質・良質脂質・ビタミン・ミネラルを意識することが大切です。
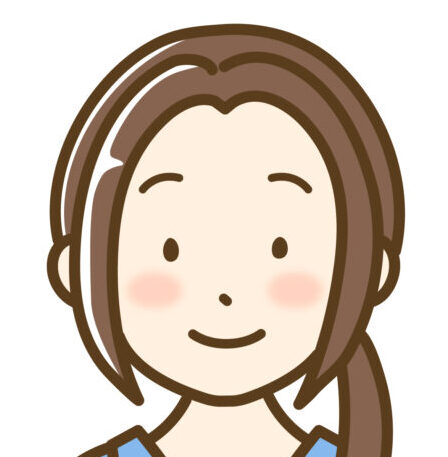
Q. 男性側も運動は有効か?
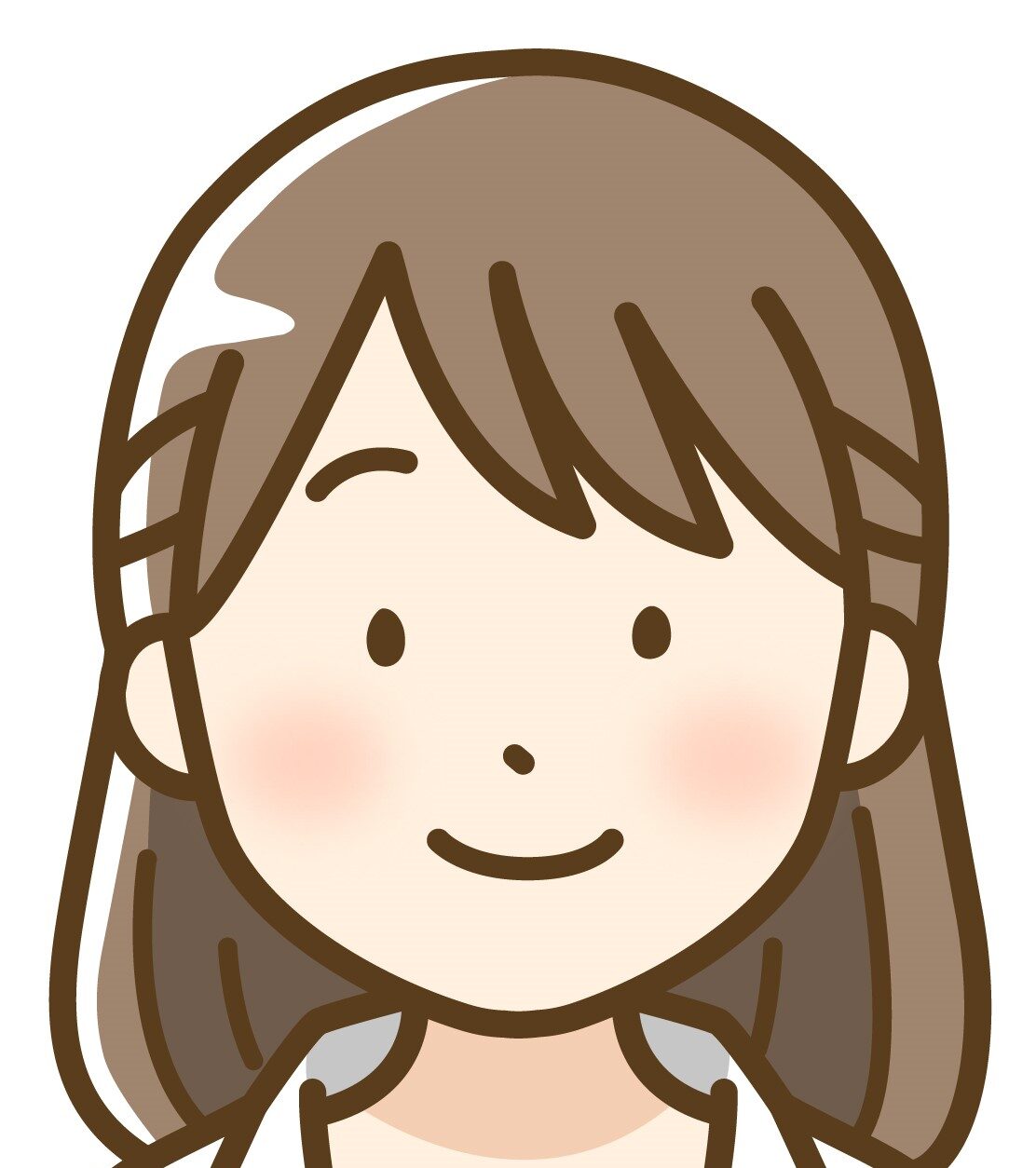
はい。男性の精子の質・運動性を改善する研究も多く、過度でない運動は有益とされます。運動により肥満や代謝異常が改善されると、男性ホルモンのバランス改善・精液パラメータの向上も期待できます。
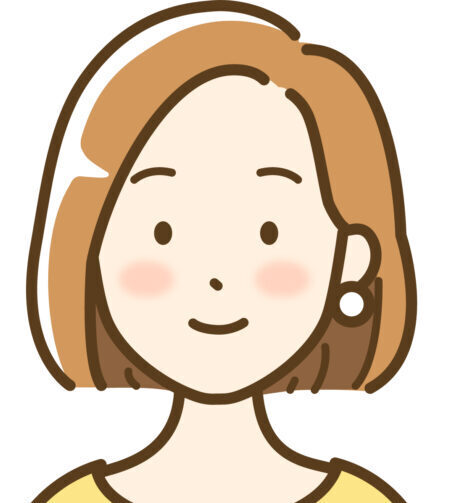
Q. 運動しても妊娠できない人はどうすれば?
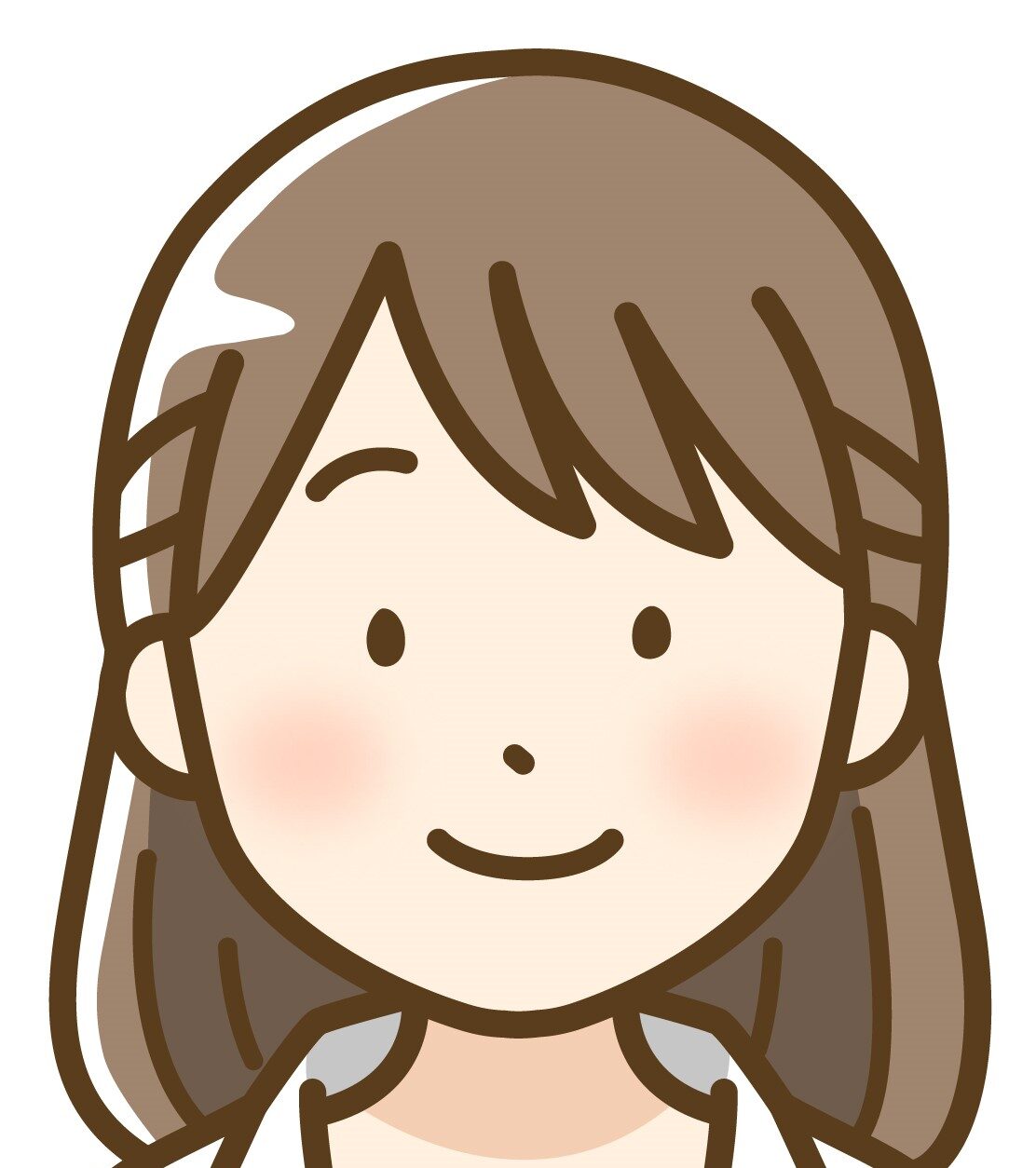
運動はあくまで妊娠力をサポートする一側面です。もし運動・生活改善を取り入れているにもかかわらず妊娠に至らない場合は、専門の不妊治療クリニックで検査・診断を受けることを強くおすすめします。ホルモン検査、卵管検査、子宮内膜検査などを通じて原因を探る必要があります。
まとめ:妊活×運動で大切なこと

- 適度な運動は妊娠力を支える味方
血流改善・ホルモン調整・ストレス軽減などの面で、妊活の下支えになります。 - “ほどほど”が鍵/過度は逆効果の可能性も
強すぎる運動は排卵系に悪影響を及ぼすリスクがあります。 - 無理のない習慣づくりが継続のコツ
ウォーキング・ヨガ・軽い筋トレなど、体への負荷が少ない運動を組み合せて。 - 治療中・体調変化期は調整と医師判断を最優先
体外受精・採卵期などは運動を制限すべき時期もあります。 - 運動だけではなく、総合的な生活改善が不可欠
栄養・睡眠・ストレス管理も含めた“妊娠モードづくり”が大事です。
妊活期間はどうしても気を使うことが多くなりますが、体を動かすことは「自分の体に向き合う時間」にもなります。小さな一歩から始めて、自分の心と体の声を聞きながら、無理なく運動習慣を育てていけるといいですね。
参考文献
厚生労働省「妊娠前からはじめる妊産婦のための食生活指針」https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a29a9bee-4d29-482d-a63b-5f9cb8ea0aa2/aaaf2a82/20230401_policies_boshihoken_shokuji_02.pdf
日本臨床スポーツ医学会「妊婦スポーツの安全管理基準(案)」https://www.rinspo.jp/files/proposal_11-1.pdf
日本スポーツ協会「妊娠期・産後期トータルサポート」資料https://www.jpnsport.go.jp/hpsc/Portals/0/resources/jiss/female_athlete/2020_joseishien-2.pdf
世界保健機関 (WHO)「身体活動・座位行動 ガイドライン(日本語版)」https://jaee.umin.jp/doc/WHO2020JPN.pdf
解説記事:「妊活における運動の効果や運動を取り入れるポイントを紹介!」https://kensui-mc.jp/blog/infertility/392/
 マタニティーユニバーシティ
マタニティーユニバーシティ 

